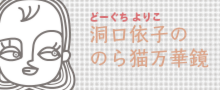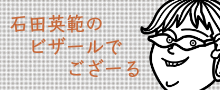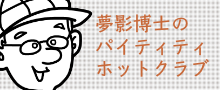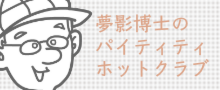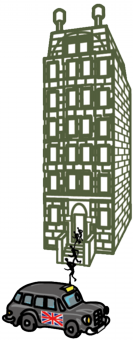![]()
![]()
![]()
![]() Wandré Model 608 Spazial Blue
Wandré Model 608 Spazial Blue
最初に紹介したいのは60年代初期のイタリア製エレキ・ギター、Wandre(ワンドレ)です。これは「ティキ・サウンド」を追求する作曲家でベーシストの佐々木謙氏が発掘した逸品。弾かせてもらって、ひと目惚れ!それを譲り受けた次第であります。このギターは50年代中期から60年代後期の10数年間、楽器作りに熱中していたイタリア人の彫刻家 WANDRE PIOLI 氏(イタリア語ではヴァンドレ・ピオリと発音するらしい)の手によるもので、彫刻家らしい独創的なフォルムを持った様々なエレキ・ギターやエレキ・ベースを世に送り出しました。形の面白さのみならず、この楽器のブライトでコクのある音色は、時を忘れて弾き続けてしまう程、飽きのこない不思議な魅力を持っています。材質の選び方や、その組み合わせがとても変わっていて、ボディーは合板削り出しですが、中が空洞。普通のギターならブリッジがついている真下のボディー部分は、常識的にはフラット・トップか、ちょっと膨らんだアーチド・トップなのですが、これはまるで逆。スプーンのように凹んでいます。その凹んだ部分に、ヘッドからブリッジまでが一体化したアルミ製の空洞ストレート・ネックが突き刺さって宙に浮いています。当時、最先端素材であった、合板、プラスチック、アルミニウム、などの加工技術を駆使して、非常識なカタチと構造を持ったギターやベースの創造に成功しています。信じられないぐらい軽いです。またボディーの模様は、キャンドルの炎から出たススを周囲から回り込むように当ててグラデーションを出しているところも面白いです。ピカソが描くギターのようでもあり、アルプのとろけた立体作品のようでもあり、たまたまギターのカタチにとどまっている「音の出る彫刻」と言ってもいいかも知れません。いままでどのぐらいのパーティーで演奏し、ラウンジを沸かせ、こぼれたワインのしぶきを浴び、アルデンテのパスタをひっかけられ、その音の中で何人の男女がキスをしたのか・・。このワンドレを抱きながら想像するだけで笑っちゃいます。パイティティのマキシシングルの収録曲「MacGuffin?」(マクガフィン?)は、このワンドレから受けたインスピレーションで一気に曲想が浮かんだ作品です。是非聴いてみて下さい。
![]() iTunesで「MacGuffin?」を試聴してみる
iTunesで「MacGuffin?」を試聴してみる

Wandré Model 608 Spazial Blue
![]()

「インド三兄弟」上から、タブラくん、ドローンくん、レヘラくん。
808(やおや)だの、909(クオーク)だの、今でこそ、こんな愛称でクラブ・トラックス・メーカーの間で親しまれるようになった日本製のリズムマシンが、世界市場に一斉に顔を並べたのは80年代初頭ですよね?。出たての頃は、内外のあらゆるメーカーのドラムマシンが街の楽器屋さんに所狭しと置いてあるのを見て、これで思う存分、自宅で「アレ」が出来る。ついに夢のような世界がやって来たなと感じたものです。反面、ドラマーという職業はこの先どうなっちゃうんだろうとも。それらのマシン達。価格もピンキリでしたが。自分ではTR-505なんてのを買って愛用していました。当時、そのTRー505を「ティアルゴ・マルコくん」などと命名し、ラテン系外人・ロボット・ドラマーとして迎え入れ、一緒になって毎晩・毎晩、眠気も忘れて自作曲作りに明け暮れたものでした。
「アレ」をやり始めたのが中1の頃。アレとは「多重録音」のことです。後に「宅録」と呼ばれるようになるアレです。70年代はマルチトラック・レコーダーなんていう夢の機材は、本格的なレコーディング・スタジオ以外に存在しませんでしたから、自宅ではラジカセ(sony スタジオ1780や1980)や、少し上等なステレオ・カセット・デッキを2台使って「多重録音」と言うものを楽しんでいました。片一方のカセットにギターのバッキングを入れたら、ミキサーを介して、いま録った演奏を聴きながら、今度はもう一台のデッキへオブリガードやソロを加えて重ね録りして行くという寸法。これを延々と繰り返すのです。これが実に楽しい遊びだったのですよ。みんなやったんじゃないかな?まあ何と言うか、音に置き換えた木版画の多色刷りみたいなものですね。何枚もの版木に絵の構成要素を色分けしてバラバラに彫って、最後にピタッと全ての版を合わせて、ひとつの絵として完成させる。こういう行いと同じだなと、美術の時間に版画を彫っていて、そう思ったのを覚えています。まあワタクシは歌が苦手だったのでほとんどインスト曲でしたが。思えばあんな6mm幅のオープンリール・テープの、その半分の3mm幅のカセット・テープの、さらに片チャンネル1.5mm幅のストライプを目がけて情熱を注いでいた頃が懐かしいです(笑)今と違って良い音でフィニッシュするのは至難の業でして・・。コツは色々あるんですが、ひとつだけ挙げるとすれば、低音楽器のベースは最後の方に入れるんです。意外でしょうが何故かと言うと、リズム隊だから当然だろうと思って最初の方にベースを録音してしまうと、ダビングを重ねるにつれ、最後にはベースだったはずの音が到底ベースの音には聴こえない、モコモコのブ-ブー潰れた音に変身してしまうことが、何度もやっていて分かったからなのです。それで必然的にベースは最後の方に入れるという作法が決まって行ったのでした。このようにカセット・テープ2台でダビングを繰り返すと、さらに、どうなるか。もうノイズの嵐です。シャーーーって。これに加えて、2台のカセット・レコーダーのピッチも微妙に違うので、最終的に音楽のキーが1音上がっていたなんていう事もざら。でも、この遊び。ひとりの演奏が、最後は何十人もの合奏になっているという、シンプルな驚きと達成感。こんな多重録音遊びのカセット・テープが、家に数百本残っているのですが・、いったい、いつ聴くんだろうこれ?(笑)おじさん世代のハズカシ遺産、宅録カセット大集合なんていう番組があってもいいかもね。誰しも30年前には戻れまい。今のレコーディング技術で奇麗に録っても意味がない。思い出深い、個人個人のサウンド・タイムカプセルというものがあるもんです。この場合、音楽の善し悪しを聴くというよりも、ノイズの向こうに見える当時の太陽の日差しの量というのかな。そういう音が聴こえて楽しいんですよ。(笑)
そもそも何故こんな事に夢中になったかと言うと、1974年に大ヒットした「エクソシスト」と言うオカルト映画がきっかけでした。当時ワタクシは中学2年。日本公開の初日に観に行こうと友達を誘っても、怖いからやだと誰も乗ってくれません。じゃーしょーがない、1人で観に行ってやろうじゃないか。と観に行ったのですが、結果はやはり・・。怖すぎる・・。あまりの恐怖にこの映画がトラウマになってしまってしまい「エクソシスト」だけは未だに1人では観られない身体なってしまいました。あーこわい。リーガン気持ち悪い・。でも、この映画のテーマ音楽は最高でした。これなんです。多重録音オタクになったきっかけは。この曲の原題は「チューブラーベルズ」作者はイギリス屈指の多重録音オタク・マスター、マイク・オールドフィールド。恐怖映画の内容とは真逆で、悲しくも美しいピアノのシーケンスで始まり、繰り返し繰り返し延々と続いて行くそのシーケンスに、色々な楽器が重なり最後は凄まじいオーケストレーションに発展して行くというとんでもない代物だったのです。何じゃ、この素晴らしい曲は。当時、映画雑誌か音楽雑誌に出ていたインタビューを読んだ記憶が正しければ、全ての楽器を自分1人で演奏し、ダビング録音した回数が2600回と書いてありました。え~、2600回も重ねたのか?。スゴすぎる。よし、明日からオレもやってみようと、こういういきさつで、さらに夢中になっちゃったのでした。
この「エクソシストのテーマ」の世界的大ヒットにより、当時のヴァージン・レコードのオーナー、リチャード・ブランソン氏が、ヴァージンアトランティック航空を設立し飛行機を飛ばすようになったというのは有名な話です。あ、余談ばかりですが、つい先日、ヴァージンから届いたお知らせを見てビックリ! ”世界で初めて、プロフェッショナル仕様のレコーディングスタジオ機器をヒースロー空港アッパークラスラウンジ「ザ・クラブハウス」内に設置しました” ・・ですって(笑)ミュージシャンが、いつどこで名曲がひらめくが分からないので、いつでもラウンジでレコーディングが出来るようにと、カワイイProToolsスタジオを設置したそうです。笑っちゃいますね〜。ちなみに、ミュージシャンじゃなくても使用可能だそうです。
こういう事を本気でやっちゃうから、ヴァージンアトランティック航空が大好き。このスタジオの存在自体がビザールそのもの。
なんか狭くて、ツーな、むかし話から始まって恐縮です(笑)インド三兄弟の話はどこへ飛んでった?
はてさて、本題です。「インド三兄弟」とは、ここ20年ぐらいの間に巡り会った、インド人・ロボット・ミュージシャンのことです。

1)「タブラくん」
インドの楽器の花形は、やはりシタールなのでしょうか?シタール奏者がどこかへ出かけて演奏するときに、一緒に演奏してくれるお友達のタブラ奏者がいない場合、日常的に、この「タブラくん」を連れて行きます。タブラとは大小2個でワンセットのインドのリズム楽器で、ひとつは木、もうひとつはアルミの胴体で出来ていて、両方ともヤギの皮が張ってあります。上の写真に写っている黒いボディーのロボット「タブラくん」は、ありとあらゆる変拍子に対応しているようで、つまみをいじっても、あまりのパターンの多さに、未だワタクシには、何が何だかサッパリ分かりません。5拍子~7拍子~3拍子~6/8拍子~9拍子なんていう感じで、ボカスカボカスカっと、連発して音が出てきます。もう日本の音楽とかアメリカの音楽とか、そんな分かりやすい次元のリズムではないですね(笑)5拍子でターメリックをフワッと撒いたかと思ったら。7拍子でカルダモンのつぶが砕け、3拍子でやっと安心のレッドペッパーがドドーンと入り、6/8拍子でクミンシードがじわっと泡だち、9拍子でヒングの強烈な香りに浸かって全員もろともニルバーナへ!(笑)このプロセスを電源を抜くまで、又は電池が切れるまで、延々に繰り返す事が出来る、彼こそが「タブラくん」スゴいヤツです。スパイシー!。
2)「ドローンくん」
ついこの前、インド人のタブラ奏者の演奏を聴く機会があったのですが、ステージを見たらタブラ奏者の隣にひっそりと置いてあったのが、これと全く同じ「ドローンくん」だったのでビックリ。タブラのソロって言うのは、指も含めた2本の手からどのぐらい音が出れば気が済むのかと思うぐらいの音数で、スゴイんですよ。このドローンくんですが、通奏低音と呼ばれる「ギュワ~~~ン、ギュワ~~~ン」と、ゆっくりうねるような音色の低い音を、延々と途切れること無く出し続ける役割の楽器なのです。その場の空気や色調を決める低音とでも言うのかな?この音は実に落ち着く、心安らぐ音で、その場を一瞬にして、白檀のお香を焚いたお寺の境内のような世界にしてしまいます。こういう音が鳴っている上で、タブラやシタールのソロをする演奏者を見ると、とても気持ち良さそうです。この「ドローンくん」の音は、シタールに似たボディーに、弦が4本張ってある「タンプーラ」と言う楽器の音のシミュレートなのですが、この「タンプーラ」、今まで、女性がなでるような手つきで弦をつま弾いている演奏風景しか見た事がないのです。撫弦楽器とでも言いたくなります。女性の細い指先で空間にドレープのような風をそよがせる楽器。何か「掟」でもあるのでしょうか?女性専用の楽器だったりして?だとしたら、なんか分かるな・・という気がします。本当なら名前は「ドローンくん」じゃなくて「ドローンちゃん」なのかも?
3)「レヘラくん」
彼の存在がいまいち分からないのです(笑)
インドでは、月や曜日によって演奏する曲が決まっていると聞いた事があります。また、同じ曲でも時間帯によってキーが変わるとも聞きました。このレヘラくんの上部パネルを見ると、SA RI GA MA PA DHA NI SA、と見知らぬ単語が書いてあったので、調べてみたら、これはインドのド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド、の事でありました。何でも良いからスイッチを押してスタートさせてみると、ん~、何といったら良いのか。全くなじみのない奇怪な音階がデルデルデル出る。これがインド音階?と言っても、ナチュラル・マイナースケールだとか、メロディック・マイナースケールだとか、アラビック・マイナースケールだとか、そんな分かりやすいものではないのです、これは。ん~、一体どう使ったら良いのか。何かの儀式に使う音階か?ナゾ謎マシーンです。ん?そうか、ちょっとだけピンと来た。たったひとつ自分なりに説明出来るとすれば(これも大変古い話で恐縮ですが)昔テレビでやっていた「悪魔くん」に出て来るソロモンの笛の音階です!。悪魔くんは、召使いのメフィストが命令を聞かなくなると、こらしめるためにソロモンの笛を吹く。それを聞いたメフィストは頭から煙を出して降参しちゃう!アレだアレだ!操作パネルを見ると、そんな曲のパターンが202通りプログラムされていると記されています(笑)わ~、大変な代物だ。正直ちょっと聞いただけでは馴染めない音階だけど、こういうのって多分「音で聴いて身体のツボに効かす」ような作用が、きっとあるんだと思う。もう、ウルティマ・スパイシーですね。
今回はパイティティの新メンバー、マサラの国からやって来た、インド3兄弟のご紹介でした。これから録音する新曲で、是非、ウクレレとの共演を果たしてみたいと思っています。過度の期待はせずに、お好きなカレーか、コロモコ、またはジューシーなアメリカンビーフ・ハンバーガーでも食べながら御待ちくださいませ・・。
![]()
![]()
![]() Dallas Banjo Ukulele George Formby Model "C/ 1940年代後期製
Dallas Banjo Ukulele George Formby Model "C/ 1940年代後期製
ウクレレ・ユニット、パイティティ。やっとウクレレの登場です。
ウクレレといえばハワイアン。もちろん常識です。でもその常識は、そもそも何処から来たんでしたっけ? ウィキペディアには、ポルトガルから来た移民がハワイに持ち込んだブラギーニャという4弦楽器がハワイで育って進化して今のウクレレになったと解説が載っていました。ブラジルにも同じ構造で金属弦を張ったカバキーニョという楽器があったそうです。ルーツは同じ。現在ハワイはアメリカ合衆国のひとつの州ですが、この楽器の名前が、ニャ、とか、ニョとか、カワイく終わっていることで、そもそもラテン系の民族楽器だったことが分かりますよね。気候風土って面白いなぁ。その土地から生まれたサウンドに必ず変身しちゃう。住んでる人のDNAとかけ合わさって、ハワイではハワイアンに変身。タヒチではタヒチアンに。青森の津軽三味線と、沖縄の三線。どちらも楽器の構造は同じなのに音楽自体が全く別物。音階も違う。本当に不思議なものですねぇ。
さて、ご存知イギリスのロックバンド、クイーンの「ブリング・バック・ザット・リロイ・ブラウン」という曲の最後の方に、ちょっとだけ顔を出すウクレレ・サウンドを思い出せるでしょうか?ブライアン・メイがかき鳴らしているあのウクレレ・サウンド。初めて聴いた時から、なんてカッコイイ・コード・ソロなんだろうと、ただただ、すごいなぁと感心していたのですが、アレが一般的な木製ウクレレではなく、バンジョー・ウクレレのサウンドだと分かったのは実は最近のことでして・・。楽器の特定もさることながら、あのスピーディーな弾き方、あの独特の雰囲気は何なんだろうと、数十年間、ずーっと頭の隅っこにこびりついて離れませんでした。ブライアン・メイはエレキ・ギターの独特な音色や奏法のみならず、ウクレレを弾いても、オリジナル・サウンドをクリエイト出来る本当に大したミュージシャンだなぁ、流石だなぁと感心していました。最近YouTubeなどであらゆる国のあらゆる音楽が簡単に聴けるようになりましたが、ネットサーフィンしていた所、あのウクレレ・サウンドそのものを鳴らしているアーティストに出くわしてしまいました。探すと、あるわあるわ。あのサウンドが。
そのサウンドのオリジネーターは、1930~40年代に大活躍したイギリス喜劇映画界の国民的大スター「ジョージ・フォーンビー」という方でした。あ~なるほど。本人の曲を聴いて納得。クイーンのあのウクレレ・サウンドは、ジョージ・フォーンビーへのしなやかなオマージュという意味合いも有ったのですね。あの曲で聴けるブライアン・メイのプレイは、ズバリ、ジョージ・フォーンビー奏法そのものだったのです。

※こちらが1940年代後期に作られたバンジョー・ウクレレ。立体写真でどーぞ。(交差視)
ひと昔前までイギリスではウクレレと言えばバンジョー・ウクレレを指していたそうです。ジョージ・フォーンビーたったひとりの影響で。1961年に亡くなったときは、国葬級だったそう。この方の映画は、主役を張りつつも、毎回、面白い歌詞を独特のバンジョー・ウクレレ奏法で伴奏しながら、変わった声で歌うんですよ。映画を観てみると、その魅力がイギリス人をノック・アウトした理由が良~く分かります。その世界感の地続きにいるのはモンティー・パイソンのエリック・アイドルやボンゾ・ドッグのニール・イネス。もろに受け継いています。もしブルースやってたらスリーピー・ジョン・エスティスやロバート・ジョンソンに行き着くんだろうけど。ん〜っ。あ〜っ。ジョージ・フォーンビーに辿り着いちゃった。まあいいか、笑。歌モノって一般的に、1番の次は間奏で、2番が終わると1番のサビが再び出て来てエンディング、と言うのがバランスの良い展開とされていますが、フォーンビーの曲は、1番、2番、3番、4番と連続で歌い続け、最後にバンジョー・ウクレレのスーパー・ソロをかまし、唖然とさせた所でいきなりスッキリ終わるという独特のスタイルを持っています。何だかマザーグースの読み聞かせの様な・・。音楽的にはワンパターンと見ることも出来ますが、これが完璧な様式美になっているので、何処からも文句は出ません。それが気持ちいいのです。ピカソやブラックがキュビズム様式の中で自由にモノを描くのと一緒ですね。スキだなぁ。

※ウクレレを包んでいた新聞を広げると、英国ロイヤル・エアフォースで飛行演習に挑むウィリアム王子の記事が。こう見るとウィリアム王子とジョージ・フォーンビーは同じ方向のお顔立ちですよね?きっとウィリアム王子も演習の合間にまるでフォーンビーの映画さながら、ウクレレと歌で仲間を楽しませていたと想像します。しかし、これほどバンジョー・ウクレレが上手くなる素質十分なルックスは貴重です。
ロンドンでウクレレやってるんだ、と言うと「ああ、ユクレリね」と英語圏の発音に言い直されます。そんな経験をふまえ、この前パリでユクレリやってますと言ったら「ああ、ウクレレね、フランスではウクレレで通じるよ」と言われてしまい、ハハン、そーか、そもそもラテン語圏生まれのウクレレがラテン語圏に戻っただけかと、合点しちゃいました。きっとイタリアでも同じだろうな。男性奏者なら「ウクレリーノ」女性奏者なら「ウクレリーナ」なんて言ってみたらカワイイくて受けるかもね。でも何で日本ではウクレレで通ってるのかなぁ? アメリカ系由で入って来たならユクレリと発音していたハズ。あ、そうか。ペリーが黒船で下田に着いたときに、ウクレレを積んでいたのだろう。多分そうだ。その頃に録音する技術が有れば、琵琶と三味線と琴と太鼓と笙とヒチリキとウクレレとか、色々遊んだ成果が聴けただろうに。バテレンさん&和服にかんざしの歌姫とチョンマゲ楽団のJAZZとか、デロリアンでバック・トゥー・ザ・フューチャーして生で聴いてみたいものです。
♡
♡
♡
長ら〜く沈黙中のパイティティでしたが、やっと新作レコーディングを開始しました。今年になってイギリスから届いたこのステキなバンジョー・ウクレレですが、録音してみたら存在感ありすぎ。目立って目立ってしょうがない。実はちょっと困ってます、笑。どーしよう。にわかフォーンビー奏法を会得するだけでもはかなりハードルが高いのでありますが、笑。でも、次作品のどこかに登場することは間違い無しです。都会の喧騒、ビルの谷間のすきま風、砂ぼこり。アスファルトの水たまり。スモッグ、通勤ラッシュ、クーラーと暖房を付けたり消したり、野外も室内も、毎日異常気象。そんな風土の中からスーッとにじみ出て来たものがパイティティのサウンドなのかもなぁと、時折、思ったりしつつ・・。ま、どんな形になるか分かりませんが、必ず新作が出ますので、どうぞお楽しみに・・・。
<バンジョー・ウクレレのお仲間紹介>
こちらはWerco製のかわいいバンジョー・ウクレレ。なんとネックがオール鉄の鋳造です。さぞ重たいかと思いきや、案外軽くてビックリ。裏返してビックリ。ウソみたいな軽量化の工夫がなされていました。60年代、鉄鋼業全盛期のシカゴで作られたウクレレらしいです。よく出来てます。と言うか、よくやるよ。まるでドイツのバウハウス出身アーティストが作ったデザイン・ウクレレと言った様相を呈していますね。デザイナーはいったい誰?

ほぼ正面。

ネックの裏側。何だかスゴいな。ターミネーターみたい。
![]()
![]()
![]() Danelectro Longhorn Baritone Guitar(6弦ベース)/ 1960年代製
Danelectro Longhorn Baritone Guitar(6弦ベース)/ 1960年代製
ダンエレクトロは1940年代後半からアメリカのデパート「シアーズ」の楽器コーナーで扱われていたブランドで、初心者でも手の届きやすい低価格のギターやベースやアンプを大量生産販売していました。エリック・クラプトンやジミー・ヘンドリックスなど、今では有名なミュージシャンも最初に手にしたのはダンエレクトロだったと言うぐらい、価格は安いが、安っぽい音がしない、独特な魅力がある楽器を次々と世に送り出す不思議なメーカーだったのです。このボディーの形、普通じゃないですよね。目立ちます(笑)。そしてこれは、見た目はエレキ・ギター、でもベースなのです。6弦ベース。(ああ、ややこしや・・)普通エレキ・ギターは21フレットなのですが、これは何故か31フレットあります。何故なんだろう。実はこれと全く同じボディーにギターの6弦用ネックが付いたモデルが最初に売り出されました。見た目はまるで一緒、でもこのギターの仕様の方は、マンドリンの音域までカバーするという特徴があることから「ギターリン」と名付けられました。これを基本形とし、その1オクターブ下のチューニングでの演奏を可能にしたのが、このロングホーン・バリトーン・ギターなのです。(実際、チューニングは様々ですが・・)アメリカン・ビザール・ギターと言えば、テスコやナショナル等、色々面白いものがありますが、性能や形からしてその頂点に位置するのが、ギターリンや、このロングホーン・バリトーン・ギターだと言っても過言ではないでしょう。ボディーでキラリと光るのはリップスティック型と言われるシングル・コイル・ピックアップ。変わった形ですよねこれ。当時、実際に存在した大量生産の口紅キャップが手に入り易かったため、それを2個組み合わせて作ることになったそうです。このバリトーン・ギター、アメリカではビーチボーイズが使用したことでブレイク。イギリスではザ・フーのベーシスト、ジョン・エントウィッスルが弾いていましたよね。
このバリトーン・ギターの音の持つ味わいがダイレクトに聴ける有名な曲は何だと思いますか? 答えを聞けば、あ、アレか!と、ポンと膝を打って頂ける方も多いと思います。それはデヴィド・リンチ監督「ツイン・ピークス」のテーマ曲です。アンジェロ・バタラメンティの幻想的な曲を支配しているあのイントロのメロディー・ライン、あれこそがこのバリトーン・ギターの音なのです。エレキ・ギターにしては音域が低すぎるし、かと言ってベースという感じもしない、この音は何だろうと思っていた方も少なくないのでは? この曲で実際にバリトーン・ギターを演奏しているのは、何と、サイモン&ガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」、ドノヴァンの「サン・シャイン・スーパーマン」、TVアニメ「ジョシー・アンド・ザ・プッシー・キャッツ」、そして、フランク・シナトラの「ニューヨーク・ニューヨーク」等、挙げたらこのページが全て埋まってしまう程、ありとあらゆるセッションに引っ張りだこだったアメリカを代表するトップ・スタジオ・ミュージシャンの「ヴィンセント・ベル」というギタリスト。実はこの方こそ、このバリトーン・ギターを始め、ご存知エレクトリック・シタール・ギターなど、その後ダンエレクトロ社から発売される全ての楽器に独創的なアイデアをつぎ込んで実現させた人物なのです。当時のミュージシャンの中には、かのレス・ポールがギタリストであると同時に、自宅でオープンリール・デッキを何台も分解してマルチトラック・レコーダー自作し、ギター分身の術のような多重サウンドの創始者になったのと同様、こうした新しいサウンドの開発に多大な貢献をした方がいたのですね。尊敬します。
※ 因にドノヴァンの「サンシャイン・スーパーマン」では、ジミー・ペイジのリード・ギターのバックで、ドノヴァンと一緒にコード・カッティングをしているのがヴィンセント・ベルなのでしょうか? 当時の楽曲には参加ミュージシャンのクレジットが無いので分からないですね・・。

※ ギリシャの竪琴をイメージしてデザインされた、1960年代製
ダンエレクトロ社 ロングホーン・バリトーン・ギター
このバリトーン・ギターの音は、パイティティのマキシ・シングルの1曲目、または、1stアルバムのボーナス・トラック収録されている「Bon Appetit」(ボナペティ)で聴く事が出来ます。でも、ここで聴ける音は必ずしもこのバリトーン・ギターらしい音とは言えないかも知れません。と言うのも、この曲のミックス時、エンジニアの西込加久見氏が「この曲の中でゴニョゴニョ唸っている低い音は何ですか?」と振り返ったぐらいですから(笑)
実はこの曲のブンブン唸っているベースは洞口依子嬢が弾いています。そもそもベース好きだと公言する彼女。実際にベースをさわったはこの時が初めてだったそうですが、ヘンテコな形のこんなベースを持った途端に気分はアゲアゲ、録音スタートと同時に出るわ出るわ、面白いフレーズが。この曲のウォーキング・ベースラインに込められたトボケた感じは、この楽器を選ばなければ得られなかったサウンドです。そして正にこれが、弾く人の人格がそのまま出た(笑)ハッピー・グルーヴだ、と言えるでしょう。楽器にはその存在自体に最初から備わった得体の知れない力があるものですね〜。
そんな訳で、パイティティでは、こういった楽器から受けるインスピレーションをとても大切にしているのであります。![]() iTunesで「Bon Appetit」を試聴してみる
iTunesで「Bon Appetit」を試聴してみる
![]()
![]()
![]() Danelectro Electric Lap Steel Guitar/ 1950年代後期製
Danelectro Electric Lap Steel Guitar/ 1950年代後期製
60年代生まれの子供のほとんどは大正テレビ寄席で大活躍した司会の牧伸二が抱える小さな楽器がら飛び出す、ゆるーくトボケたサウンドでウクレレという楽器の存在を知ったのではないでしょうか?。その時既に大人だった方々は、ビアガーデンやレストランなどでウクレレの名手・大橋節夫率いるハニー アイランダースなどのカッコイイ生演奏に触れて本格的なハワイアンを知ったのではないかなと推測します。当時はラジオやテレビからたくさんハワイアンが流れていたことでしょう。僕らが住んでるここ日本に於ける第一次ハワイアン・ブームは1955年から1965年らしいですが、60年代の東京のデパートのレストランでは、普通に食事をしながら普通にハワイアン・バンドの生演奏が聴けました。もちろん無料です。今では夢のよう。
どこだったかなぁ・・、場所の記憶が無いのですが、家族で昼食をとるためにデパートの最上階のレストランに入ると、円形ステージの上にたくさん楽器が並んでいて、ステージ袖のめくりには「ダニー飯田とパラダイス・キング、2時から」と書いてありました。食事をしていると、ちょうどいいタイミングで演奏が始まったのですが、この時に聴いた演奏で特に目立っていたのがペダル・スティール・ギターの音。ちょっとコミカルなそのサウンドに子供ながらブッ飛んだ覚えがあります。なんだ?このウニャウニャ、ニャーニャー、猫の鳴き声のような楽器は?天国行きエキスプレスに乗ったような気分にさせる、ヒュィ~ン、というサウンドは?エレベーターに乗って上がったり下がったり、あっちへ、こっちへ、フワフワ。今座っている椅子がフッと消えて無くなっちゃった様な感覚。何だか三半規管がおかしくなっちゃったような快感。そんな演奏を聴きながら食事なんかしちゃう世界。へぇ~とてもイイ感じ。何曲か演奏が続いた後、突然ダニー飯田さんの「それでは本日の特別ゲストをステージにお招きしましょう、九重佑三子さんで~す」というアナウンスがあり、「え?、誰だろう?」と思いきや、顔を見てびっくり「わぁ!コメットさんだ~!」と、大はしゃぎした覚えが。その時はさすがにコメットさんの主題歌は歌ってくれませんでした。でも、あれがハワイアン・バンドの音を初めて体験した日だったのかと、時々思い出します。高度成長期の日本って、音楽面だけをとっても、そこら中に贅沢なサービスがあったのだなぁ。昔は良かったなーと、大声で言わせてもらいたい体験ですね・・。笑。
10年以上前ですが、レッド・ツェッペリンのベーシスト、ジョン・ポール・ジョーンズのソロ・コンサート「Zooma」を渋谷公会堂で観たとき、予想外にもラップ・スティールを多用した曲が多くて面食らったことがあります。しかもメチャメチャ上手くてビックリ。プレイの傾向としては、ピンク・フロイドのコンサートでデヴィッド・ギルモアがやるあの感じと同じレベル。いや、それ以上だったかも。アメリカ勢だとライ・クーダーとデヴィッド・リンドレーが名手として名高いですが、どちらにしても自分達の作る音楽にピッタリとマッチした、高レベルの演奏であることは間違いありません。あんな風に弾けたら楽しいだろうなぁ。
スティール・ギターって、ちゃんと弾けるようになるには相当な修行が必要ですが、その半目、遊びながら変な音を出しているだけでも時間を忘れて楽しめちゃう。パイティティではもちろん、後者の遊びながらを優先しています。笑。このダンエレクトロ・エレクトリック・ラップ・スティールの音は、パイティティの1stアルバムの「チャチャチャ・アイランド」で聴く事が出来ます。いつも無言のファルコンにラップ・スティールを渡した途端、カモメのような鳴き声でしゃべり始めたのであります。
iTunesで「Chachacha Island」を試聴してみる
♦
♦
♦

※ヘッド部分がトボケた顔のように見えてカワイイと思いませんか? 1stアルバムの表紙のイラストにちゃっかり登場しているので探してみて下さい。実はこのラップ・スティールはダンエレクトロの中でも探すのがとても難しい一品なのです。日本のウェブサイトで実物写真が載るのは、もしかしたら初ではないかな・・・。うふふっ。
![]()